2025年NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、江戸時代の出版王・蔦屋重三郎の生涯を描いた作品です。横浜流星さん主演で、喜多川歌麿や葛飾北斎を世に送り出した”江戸のメディア王”の成長物語が展開されます。 本記事では第1話から第5話までの詳細なあらすじと見どころを解説いたします。
『べらぼう』あらすじ 第1話「ありがた山の寒がらす」- 蔦重の運命を決めた出会い
明和9年(1772年)、江戸を襲った明和の大火から1年半が経過した吉原が物語の舞台です。茶屋で働きながら貸本業を営む蔦屋重三郎(横浜流星)は、まだ何者でもない青年でした。
第1話の最大の見どころは、蔦重と吉原の現実との衝撃的な出会いです。花魁道中で華やかさを演出する一方で、場末の河岸見世では女郎たちが悲惨な境遇に置かれている現実を目の当たりにします。特に朝顔という女郎の死は、蔦重の人生観を大きく変える転機となりました。
火事場面から始まる冒頭15分は圧巻の映像美で、江戸の町の活気と混沌を余すところなく描写しています。横浜流星さんの演技も冒頭から全開で、蔦重の持つ正義感と商売人としての鋭さが見事に表現されていました。
この第1話で注目すべきは、後に蔦重の人生を大きく左右する田沼意次(渡辺謙)との出会いも描かれることです。まだ素性を明かさない意次との会話シーンは、後の展開を知る視聴者にとって特別な意味を持ちます。
『べらぼう』あらすじ 第2話「吉原細見『嗚呼御江戸』」- 平賀源内との運命的な出会い
第2話では、蔦重の出版業への第一歩が描かれます。吉原復活のため、年に2回発行される『吉原細見』に注目した蔦重は、その「序」の部分に平賀源内(安田顕)の文章を載せることを思いつきます。
最も印象に残ったのは、蔦重と花の井(小芝風花)の微妙な距離感でした。幼なじみでありながら、遊女と客という立場で向き合わざるを得ない二人の関係性には、現代では想像しにくい複雑さがあります。花の井の気高さと蔦重への思いやりを表現する小芝風花さんの演技は、言葉以上に多くを語っていました。
平賀源内を探して江戸中を駆け回る蔦重の姿を見ていると、後の出版王としての行動力がすでに芽生えていることが分かります。湯島の長屋で炭売りの「銭内」と名乗る男(実は源内)と出会うシーンは、一見コミカルながら、身分を隠して庶民の中に身を置く源内の人間性を垣間見せる重要な場面でした。
長谷川平蔵の恋心を利用して紙花を撒かせる蔦重の手法は、顧客心理を巧みに読む商売人の嗅覚を感じさせます。現代のマーケティングにも通じる、適切なタイミングで相手の心を動かす技術といえるでしょう。
『べらぼう』あらすじ 第3話「千客万来『一目千本』」- 錦絵出版への道筋
第3話は蔦重の出版業への本格的な参入を描く重要なエピソードです。源内に吉原細見の序文を依頼する一方で、蔦重は錦絵の出版にも目を向け始めます。
駿河屋(高橋克実)に自作の人情本を持参するシーンは、蔦重の文才と商才を同時に示す巧妙な演出でした。まだ無名の蔦重が、いかにして業界の重鎮たちの信頼を勝ち取るかが丁寧に描かれています。
「一目千本」という作品を通じて、蔦重が絵師・北尾重政の才能を見抜く眼力を持っていることも示されます。これは後に喜多川歌麿や葛飾北斎を世に送り出す蔦重の先見性を暗示する重要な伏線です。
唐丸(渡邉斗翔)との友情も第3話の見どころの一つです。幼い頃から蔦重を支える相棒として、唐丸の存在は物語に温かみを与えています。二人の掛け合いは自然体で、視聴者にほっとひと息つかせる場面を提供していました。
『べらぼう』あらすじ第4話「『雛形若菜』の甘い罠」- 地本問屋の洗礼
第4話では、蔦重が地本問屋の世界の厳しさを初めて体験します。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)から『雛形若菜』の出版を持ちかけられるものの、そこには思わぬ罠が仕掛けられていました。
ここで描かれる江戸時代の出版業界の利権構造は、どの時代にも見られる人間関係の縮図です。表向きは協力的に見える同業者たちの腹の探り合いが、リアルな人間ドラマとして展開されているのが見事でした。
渡辺謙さんが演じる田沼意次の政治的駆け引きも圧巻です。平賀源内を利用した策謀の中で、蔦重も知らず知らずのうちに巻き込まれていく展開は、権力の怖さを実感させます。渡辺謙さんの存在感は別格で、画面に登場するだけで空気が一変する迫力がありました。
「地本問屋の定め」という障壁に直面した蔦重の反応からは、新参者が既存業界に参入する際の普遍的な困難が読み取れます。ここで見せる蔦重の機転と粘り強さこそが、後の成功への重要な布石となっているのです。
『べらぼう』あらすじ 第5話「蔦に唐丸因果の蔓」- 友情と裏切りの狭間で
第5話は、蔦重にとって最も辛い試練の一つが描かれます。相棒の唐丸が突然姿を消し、蔦重は友の身を案じながらも事業を進めなければならない状況に追い込まれます。
唐丸の失踪の背景には、呉服屋からの圧力と金銭的な困窮がありました。これまで蔦重を支えてきた唐丸が、逆に足手まといになることを恐れて距離を置こうとする心情が痛々しく描かれています。
このエピソードで胸を打たれたのは、蔦重の人間的な成長です。事業の成功だけでなく、大切な人との関係を維持することの難しさを学ぶ蔦重の姿は、現代を生きる私たちにも深く響きます。友情と野心の間で揺れる心境は、誰もが一度は経験する普遍的な葛藤でしょう。
「謎の絵師」についての蔦重の発言も興味深い伏線でした。この一言が後に登場する東洲斎写楽への布石だとすれば、脚本家の緻密な構成力には脱帽です。
まとめ – 出版王への序章が描く人間ドラマの深さ
第1話から第5話までを振り返ると、『べらぼう』は単なる成功物語ではなく、江戸時代の出版文化を背景にした深い人間ドラマであることが分かります。蔦重の成長過程で描かれる友情、恋愛、商売の駆け引きは、現代の私たちにも通じる普遍的なテーマです。
横浜流星さんをはじめとする豪華キャストの演技力も作品の魅力を大いに高めています。安田顕さんの平賀源内は特に秀逸で、知識人でありながらどこか庶民的な親しみやすさを併せ持つ人物として描かれ、視聴者の心を掴んで離さない魅力がありました。
これから先の展開で、蔦重がいかにして「江戸のメディア王」へと成長していくのか、そして数々の著名な浮世絵師たちとの出会いがどのように描かれるのか、期待は高まるばかりです。各話の丁寧な人物描写と時代考証により、視聴者は江戸時代の文化の香りを存分に味わうことができる、まさに大河ドラマの醍醐味を体現した作品となっています。
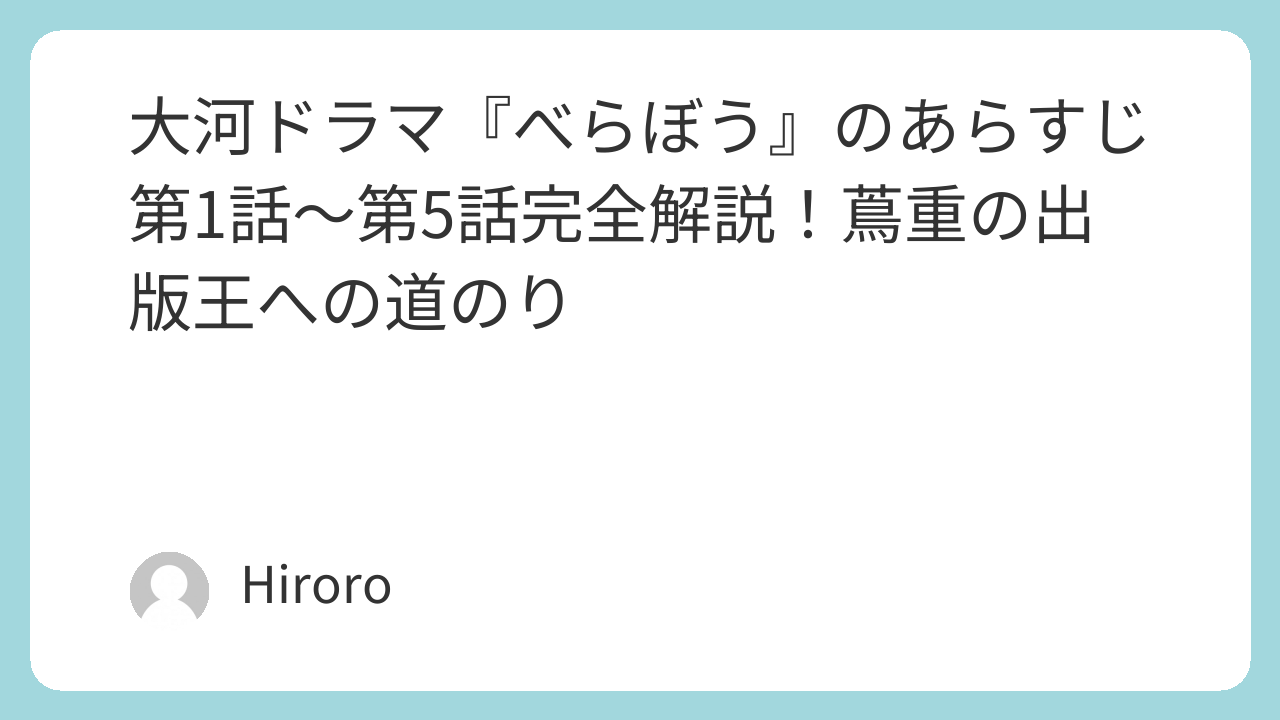
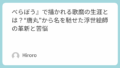
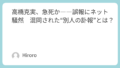
コメント