江戸の出版界を舞台とした大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。物語後半の重要な局面となる26話から29話では、米価高騰による社会不安と田沼意知の悲劇的な最期、さらに蔦重による新たな創作活動が描かれます。本記事では、これらの激動のエピソードを詳しく解説いたします。
『べらぼう』あらすじ 第26話「三人の女」- 家族の絆と商売の知恵
第26話では、浅間山噴火の影響による米価高騰が江戸の人々を苦しめる中、蔦重の実母つよ(高岡早紀)が登場します。下野で髪結いをしていたつよが生活困窮のため蔦重を頼ってくる展開は、家族の複雑な関係を浮き彫りにしました。
注目すべきはつよの商売上手な一面です。無料で髪を結いながら本の宣伝をする発想に、蔦重も即座に反応して売り込みを始める場面は微笑ましく感じました。親子の息の合った様子から、血のつながりの強さが伝わってきます。
米価高騰は政治的な問題でもありました。田沼意次が徳川治貞から叱責を受ける場面では、当時の幕政の厳しさが浮かび上がります。息子の意知がその姿を目の当たりにして、蔦重に米価対策の知恵を求めに来る展開は、政治と商売の垣根を越えた人間関係を象徴していました。
一方、ていが出家を考えて寺に身を隠す展開には胸が痛みました。蔦重の「誰とも添い遂げる気がなかった自分が目利きしたひとり」という告白は、ようやく本物の夫婦になる二人の心境変化を見事に表現していたと感じます。
『べらぼう』あらすじ 第27話「願わくば花の下にて春死なん」- 運命の歯車が回り始める
第27話は、物語が大きく動き出す前の、静かだけど不穏な空気に満ちた回でした。佐野政言の内面が少しずつ蝕まれていく様子が丁寧に描かれていて、見ているこちらも少し息が詰まるような感覚になりました。
この回で印象的だったのは、蔦重とていが一緒に米価対策を考えるシーンです。「これは商いじゃなくて政治だ」という蔦重の言葉には、商人としての意地と、社会に対する責任のようなものが感じられて胸に残りました。日本橋の商人たちが力を合わせて幕府に働きかける姿からは、江戸時代の町人たちのしたたかさと底力を感じます。
一方で、佐野政言が鷹狩りで失敗した場面や、謎の男の登場など、不気味な雰囲気もじわじわと広がっていました。咲かない桜と父からの叱責、そして夜に刀を研ぐ政言の姿には、彼の心のざわめきがにじみ出ていたように思います。
誰袖の身請けが決まり、意知との関係がひと区切りついた場面もこの回のみどころのひとつです。重三郎が語った「共に過ごす時間」にまつわる言葉が、その後の展開を思うと、どこか切なく響いてきます。
『べらぼう』あらすじ 第28話「佐野世直大明神」- 衝撃の悲劇と それぞれの仇討ち
第28話では、ついに田沼意知が命を落とすという大きな出来事が描かれました。佐野政言が江戸城内で刃傷に及んだ場面より、物語の空気が一気に変わった気がします。
なかでも心に残ったのは、瀕死の意知が父・意次に語った最後の言葉です。誰袖を気遣うやさしさと、自分の描いていた蝦夷地計画への思いを弱々しくもはっきり伝える姿には、彼の誠実な人柄がにじみ出ていました。これまで冷静でどこか距離のあった父子の関係が、この場面では痛いほど近く感じられ、意次の苦しむ表情が今でも忘れられません。
葬列の途中で民衆が石を投げ、誰袖が棺を守ろうとして傷を負う場面は、正直ちょっと目を背けたくなるようなつらさがありました。意知の死に直接関係のない人にまで怒りが向けられてしまう現実の理不尽さ。その中で誰袖が見せた覚悟のようなものに、思わず息を呑みました。
一方で、重三郎が仇討ちの代わりに黄表紙というかたちで真実を伝えようとするくだりには、彼らしさを感じました。剣ではなく言葉で立ち向かおうとするその姿勢は、商人としての決意を感じさせます。しかし須原屋の反対でそれが叶わなかったとき、時代のルールの厳しさ、そして現代と同様に傾いた世論を覆すことの難しさを感じました。
そして最後、意次が重三郎に宛てた手紙の中で、「意知の意志を継ぎ、意知が成したであろうことを成していく」と語る場面。そこには、父としての哀しみを押し殺してでも歩みを止めないという、政治家としての意志が込められていて、なんともやるせない気持ちになりました。
『べらぼう』あらすじ 第29話「江戸生艶気樺焼」- 笑いによる新たな挑戦
第29話では、蔦重が意知の死を契機に新たな創作へと踏み出します。彼が世に送り出した黄表紙『江戸生艶気樺焼』は、直接的な批判を避けつつ、笑いを通じて世の中に鋭い問いを投げかける――そんな、蔦重なりの仇討ちとも言える作品でした。
江戸の町には笑いが広がり、これまでの重苦しい雰囲気が一変。蔦重の出版人としての真骨頂が光り、その作品が人々の心に火を灯した瞬間は、観る者の胸にも深く残ります。
誰袖もまた、この作品に触れてついに笑みを見せます。蔦重が「彼女を笑わせたい」という一心で描いた物語は、その願いを見事に叶え、沈んでいた彼女の心に笑顔を取り戻させました。さらにその直後、庭に季節外れの桜が咲き乱れ、一片の花びらが静かに舞い落ちます。まるで意知が「許す」とそっと語りかけているかのような演出は、胸を打ちました。
一方、松前家の裏帳簿という重要な証拠を手に入れる展開も描かれ、蝦夷地をめぐる政治的動きが新たな局面を迎えます。時代の転換期に向けて、登場人物たちの思惑や葛藤がますます交錯していく様子から、今後の展開にも目が離せません。
まとめ – 激動の時代を生きる人々の姿
26話から29話は、米価高騰という経済問題から始まり、政治的な対立、そして主要人物の悲劇まで、様々な要素が複雑に絡み合いながら物語が進みました。
蔦重という人物の魅力は、どんな困難な状況でも創作への情熱を失わない点にあります。家族問題、社会不安、友人の死といった試練を乗り越えながら、常に新しい表現方法を模索し続ける姿には心を動かされました。
田沼親子の政治への取り組みも、単なる権力闘争ではなく、民のためという理念に基づいていることが伝わってきます。しかし民にはなかなかその想いが伝わらず、意知の死によってその志も途絶えるかと思われましたが、意次の「生きて成し遂げる」という決意に、強い意志を感じました。
一連の事件の裏に関与する黒幕の存在も気になります。今後の展開にも目が離せません。
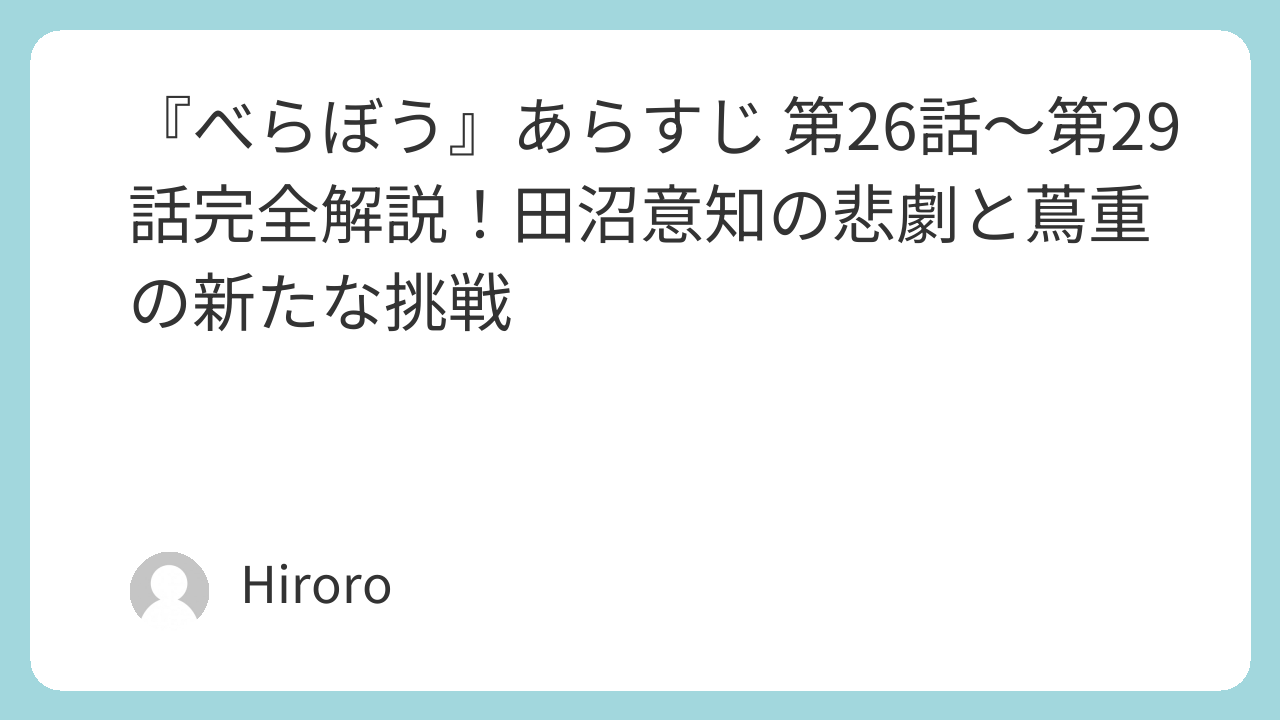
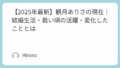
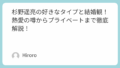
コメント